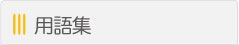アダルトチルドレンの日本での展開 |
|---|
| 1981年クラウディア・ブラック(Claudia Black)が書いた『It will never happen to me』が、1989年に齊藤學によって『私は親のようにならない』という邦題で翻訳され、これによってアダルトチルドレンという概念が日本に入ってきました。 そのときまで、この概念が生まれた国アメリカでは10年以上も、この語をめぐってさまざまな動きがあった(「アダルトチルドレンの由来」の項を参照)のですが、日本ではそうした段階を経ずにいきなり「アダルトチルドレン」という語に出会ったために、様々な混乱が生じました。 まず、生きづらさという問題を解決するための出発点であるAC概念を、ゴールと考える誤解が起こりました。こういう誤解を持っている人々は、 「わたしはACなんだから、こういうことはできなくて当たり前じゃん」 と自らを被害者と認めさせるために乱用したものでした。 また自覚用語という概念が理解されませんでした。 「わたし(たち)はアダルトチャイルド(-チルドレン)だ」 と、自分たちのために使われる言葉であったのに、 「彼女はACだ」 「あいつらはアダルトチルドレンだ」 などと、いろいろな他人をレッテル貼りするのに都合のよい言葉として誤用されてしまいました。 そこから転じて、 「自分の家庭もひどかったのに、自分はACの仲間に入れてもらえない」 と見当違いな嘆きを語る人々もあらわれました。 いっぽうでは、その語感から「子どもっぽい大人」「オトナ子ども」といった安直な受け取られ方をされ、医療にかかわる専門家、メディアにかかわる知識人までも、アダルトチルドレンという概念をよく学びもせずに批判を展開しました。 そこには「何でも親のせいにするな」「流行だから名乗るのか」というような浅はかなものから、機能不全家族の尺度をはかる指標がないなどのエビデンスベイズドなものまで、多岐にわたる批判がありました。 また、 「ACというレッテルを貼られてたまるか。おれの人生はおれのものだ」 といった、AC本人の立場から見当違いなとらえ方をする人も多くあらわれ、実際にそういう観点から何冊か本も書かれました。 このように、ACという語は誤解と乱用を含めて1990年代の日本に急速に広がりました。 こうした動きは、「ACブーム」「ACバッシング」などと呼ばれますが、いずれもAC概念を誤解したまま起こっているところに共通点があります。 そのため、いずれもAC概念を理解したうえで1980年代に展開された、アメリカのACムーブメントとは、まったく性格の異なる現象でした。 このような現象が続くなかで、やがて「自覚用語」という属性だけが肥大して突き詰められ、今度は、 「ACは、自分自身を語るときにおいてのみ使われるべきである。なのに、なぜ治療者や療法家が口にするのか」 といった教条的な批判が起こってきました。 このため、この語を日本に導入した齊藤學自身、1998年にはあいそを尽かしてしまい、自らこの語を使わなくなってしまいました。 そのかわりに、1998年には、アダルトチルドレンがもともと持っていた意味をひきつぐ言葉としてアダルトサバイバー adult suivivor が考案されました。 結論からいうと、この語は良くも悪くもアダルトチルドレンのような広がりを見せず、もともと犠牲者(victim)に対する生存者という語であるサバイバー(survivor)という語に集約され、虐待やトラウマなどの被害から生き残った者という意味で定着していきました。 アダルトチルドレンは医学用語ではないので、嗜癖問題や家族療法をあつかう専門家も、ACという語を避け、外傷性精神障害、解離性障害、PTSDといった専門用語を使う傾向があります。 しかし自助グループなどの現場では、今もアダルトチルドレンという言葉はよく使用されています。しかも、かつてACブームにわきかえっていたころのような誤用や乱用ではなく、1980年代にアメリカで使われていたのと同じような、いわば正しい意味合いで使われているようです。 |